12月30日、東京時間の夕方だが、ここでゴールドも振り返っておこう。
2013年、ゴールドは大きな下落を見せたが、これは必然でもあった。
当方としては、このブログで何度もゴールドに対して警鐘を鳴らしてきた。
金(ゴールド)について再び考える。ソブリンと金融緩和縮小の観点。 (2013年6月28日付)
金の相場の下げが意味するもの (2013年4月11日付)
メイン・ビューは先進国の通貨への信認の回復だ。
サブプライム危機による米ドルへの不信。
欧州債務危機によるユーロへの不信。
ソブリンを信じられない期間が続いたからだ。
ドルとユーロへの不信がゴールドへの需要を高めてきたのである。
それが2012年までのゴールドの大相場の原動力だ。
2013年はこれの逆回転だ。
もうユーロ崩壊を懸念している人はいない。
そしてアメリカの、ドルの本格的な復活が迫っている。
2014年、値ごろ感でゴールドを買うのはやめておいたほうがいい。
2013年 金地金 カナダ メイプルリーフ金貨 1/4オンス oz Gold Maple Leaf $10 コイン 並行輸入品
posted with amazlet at 13.12.30
カナダ造幣局
売り上げランキング: 183,708
売り上げランキング: 183,708






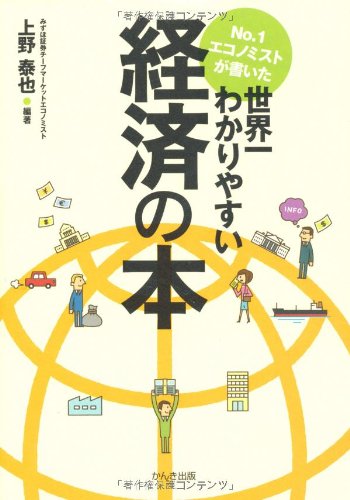
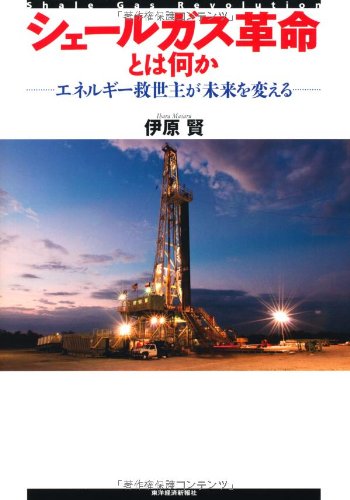
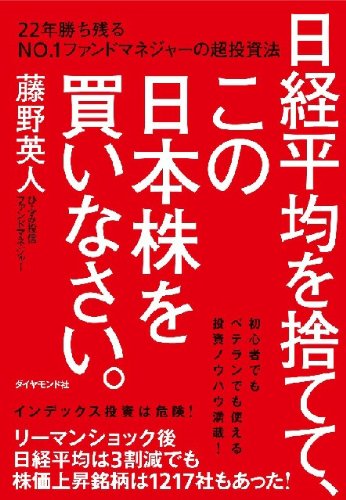


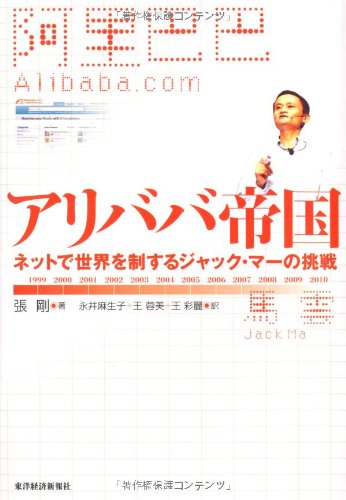

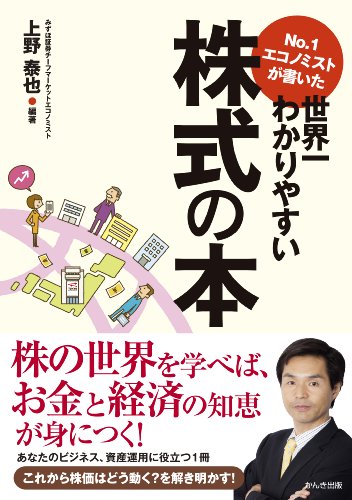


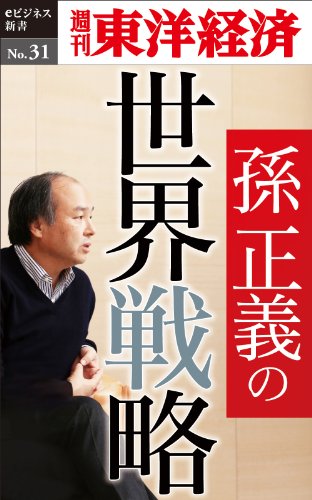
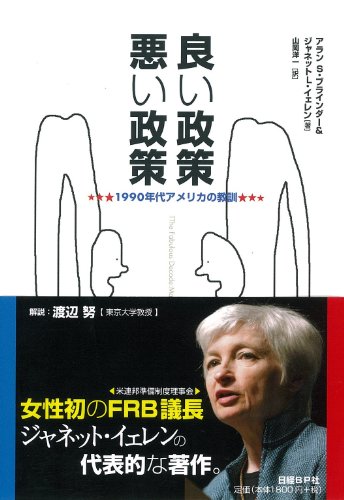
+3+%E6%97%A5+3+%E5%88%86+2013-11-14+09-52-00.jpg)



++%E6%97%A5%E8%B6%B3+31+2013-10-31+08-55-20.jpg)
++%E6%97%A5%E8%B6%B3+2013-10-28+13-44-01.jpg)











+++2013-08-29+12-46-28.jpg)
+++2013-08-29+12-45-14.jpg)




+++2013-08-21+14-00-01.jpg)








